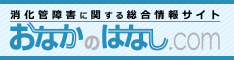今回は、胃がん検診に関してこの項で触れて頂きたいと思います。
ご承知のように、日本は歴史的に胃がんの罹患率及び死亡率が世界的に高く、そのための国家規模の事業としての、独自の検診が進められてきた経緯があります。
ところで、ここ最近、胃がん検診の方法が見直されようとしている潮流の変化をご存じでしょうか。従来、バリウム検査(正式には上部消化管X線造影検査)が主流でしたが、ここ数年、それに代わって内視鏡検査が採用される動きが見られています。特に、企業検診では地域検診よりもその傾向が顕著なようです。
では、長年にわたり重用されてきたバリウム検査での胃がん検診は何故、見直されようとしているのでしょうか。それは、胃(というより咽頭~食道~胃~十二指腸)の検査法として、内視鏡検査(胃カメラ)が広く普及してきたということと無関係ではない筈です。バリウム検査では、流れてきたバリウムが他の部分より深く濃く溜まれば、潰瘍などのキズないしは窪みを意味し、逆に周囲より明瞭なバリウムのはじきが生じておれば、ポリープなどの隆起性の変化として読み取れます。しかしながら、病変の高低が明瞭ではない場合、つまり限りなく平坦な変化であった場合は、病変の指摘は困難となります。さらには、内視鏡で、単に発赤(粘膜の赤み)や褪色(周囲より白っぽく色が抜けた状態;比較的悪性度の高いがんのことがあります)に対するバリウム検査での病変指摘は理屈からいうと、ほぼ不可能となります。
では、従来の胃のバリウム検査はもはや無意味なのでしょうか。
確かに、内視鏡検査と対比すると、上述してきましたいうに細部の観察においては僅かな変化の指摘は困難な場合があったり、放射線被爆が有りますので妊娠されている方は検査そのものが出来ませんし、そもそもバリウム自体飲みやすいものではない上に、検査後下剤を飲まないと便秘や下手をすると腸閉塞になりかねないといった、リスクをも生じかねません。しかし、バリウム検査では、微細な変化は捉えにくくても、胃から食道へのバリウムの逆流により《食道裂孔ヘルニア・胃食道逆流症》、胃粘膜のざらつき(専門的にはアレアの粗造などと表現されます)や皺の太まり・蛇行により《慢性萎縮性胃炎》が診断されます。さらには、内視鏡検査でも確定診断が困難な場合もある、いわゆるスキルス胃がんの胃壁の進展具合の悪さの指摘はバリウム検査の方が一目瞭然ということも有ります。もともと、内視鏡は細径化したとはいえ、液体のバリウムとは比較にならないくらい喉触りは良いものではなく、内視鏡にハードルの高さを感じておられる方には、一次検診としては比較的受け入れやすい方法論としての地位は揺るがないように思われます。
内視鏡検査の高画質化(更には特殊光観察、拡大観察等の併用)は検査の精度を高め、スコープの細径化や経鼻挿入は受診者の忍容性を向上させ、益々内視鏡検査の必要性は増すものと思います。一方で、胃検査の敷居を下げる役目もあるバリウム検査は胃がん検診から消えてゆく存在になるのではなく、内視鏡検査と並列で選択可能なオプションとして、また50年以上もこの国の胃がん検診を支えてきた歴史ある検査手法として、存続されることを個人的には望みます。はじめから内視鏡は嫌だけど、一次のバリウムで引っかかったから、二次では意を決して内視鏡検査を受けようか、というのもアリだと思うのですが。如何でしょうか。
追伸
とはいうものの、残念ながら当院もバリウム検査の設備はなく、専ら内視鏡検査一辺倒ですので、説得力が無いことをお詫びいたします。